12/15(金) ついに登場★HPLC(高速液体クロマトグラフィー)
12/11(月) obmでTV番組の取材と撮影をして頂きました

12/6(水) きれいに色分けできました♪オープンカラムで色素分離実験


12/4(月) obmでインスタ映え写真
11/30(木) 人気 OCレポート
OCレポート 人工いくらを作ってみよう
人工いくらを作ってみよう
11/29(水) 色素を分離して分析しよう!クロマトグラフィー実習
11/27(月) バイオ学科在校生 ~環境分析実習~
~環境分析実習~
みなさんこんにちは!
入試広報部
バイオ学科・バイオ技術学科
担当の佐久間です![]()
今回はバイオ学科在校生の
環境分析の実習におじゃまさせて
いただきました![]()
バイオ学科(3年制)には
環境分析技術者を目指す
環境科学のコースがあります
環境分析技術者とは?
★環境保全や公害防止を目的とした
測定・調査・分析の技術を持っている。
皆さんのまわりにある水・大気・土壌など
何一つ欠けても安心安全な生活を送ることは
できません![]()
そうした水・大気・土壌保全など
エコの様々な分野で重要度の高まっている
技術を習得し将来は人々の生活安全
地球環境を守っていく環境分野の技術者を
めざします![]()
今回在校生はキレート滴定という方法で
水の硬度を測っていました![]()
水の硬度は水の中に含まれている
マグネシウムやカルシウムが決めています
なんか見たことあるぞといいう
馴染み深い水たちです![]()




硬水(マグネシウムイオン・マグネシウムイオンが
含まれています)
+指示薬EBTにより赤色になっています
そこにEDTA水溶液を加えていきます。
赤色から青色へと変化します
なぜ色が変化するかというとまずは
カルシウムイオン・マグネシウムイオン
+指示薬EBTが仲良くしている状態(赤色)
からカルシウムイオン・マグネシウムイオン
EDTAが仲良くしている状態(無色)になります
滴定完了ともに色はカルシウムイオン
マグネシウムイオンと離れたEBT指示薬に
より青色になるというわけです
(pH=10付近の水溶液中でEBTは青色になる)
ということで赤色→青色へと色が変化![]()
EDTAはEBT指示薬より
カルシウムイオンやマグネシウムイオンと
仲良しなんですね![]()
実は環境の分野以外でも
細胞培養の分野でのEDTAを
使います![]()
細胞を培養する上で培養している容器から
細胞をはがすことが必要になります![]()
カルシウムイオンやマグネシウムイオンがあると
細胞は容器からはがれにくくなります![]()
EDTAはその二つのイオンとくっついて
働かなくする作用(キレートという)ができる
優れもの!
色んな分野で活躍しているんですね![]()
生徒の実習の様子もムービーで撮影したので
良かったら見てくださいね![]()
11/19(日) 色の分析体験 ペーパークロマトグラフィー
ペーパークロマトグラフィー
入試広報部
バイオ・バイオ技術学科担当
佐久間です
今回は色の分析体験の
オープンキャンパスレポートです

分子レベル(色素などの小さいもの)
で混ざり合っているものを
分析するための方法に
クロマトグラフィーという方法があります
今回はクロマトグラフィーの中の
ペーパークロマトグラフィーの
原理を使って色ペンの色素を
わけてみました
今回の体験授業はバイオ技術学科(2年制)で
実習を担当していただいている
石先生が登場

在校生も体験授業をサポートしてくれました
ありがとうございます

在校生の自己紹介タイムもはさんで
それでは体験授業スタート
色のスタート地点となるところに
線を引いていきます

水に浸して色を分けるので紙コップに水を入れます


ろ紙に各自好きな色ペンで●を書いて
水に浸すとあら不思議 色が分かれます
皆さんも美術の時間などで
絵の具を使ったことはありますよね
あお、ぴんくなども色んな色が
混ざってできています
ではなぜ色がわかれたのか・・・?
その仕組みをさぐってみましょう
【毛細管現象】
水がろ紙にしみこんで上に染みわたっていくことを
毛細管現象と呼びます
水がどんどん上に上がっていくということは
ろ紙の中を水が流れていると想像できます
色ペンの色素は水に溶けるので
その水に流されていくわけです

その流れていく中でこの写真を見ると
色が流されている距離が違いますよね
この色ペンの色を構成しているのは
色素という色をつけた分子です
実は分子レベルで色が違うだけでなく
色ごとによって水やろ紙との
親和性が違うんです
親和性=仲良し度のようなものです
なのでろ紙との親和性が高い色ほど
ろ紙にくっついていたがるのでそれほど
距離は伸びません
水との親和性が高い色ほど
水とくっついていたがるので
流される距離がながくなる
ということなんですね
今回は
ペーパークロマトグラフィー
という原理を利用して体験授業を
行いました
他にもobmにあるような
液体クロマトグラフィー(HPLC)など
様々なクロマトグラフィーが存在します
今回はろ紙や水を使って色を分けましたが
そのろ紙や水の部分が各クロマトグラフィーに
よって違うというわけですね
バイオの分野でも色々なものを生産
分析するためにこの原理が使われています
クロマトグラフィーという方法は
100年ぐらい前に発明された方法です
名前の由来は「色」と「記録する」という
意味のギリシア語からつけられたそうです
obmでは分析の勉強をすることができます
分析のための分析教室もあり最新の機材を
使って生徒の皆さんが実習に取り組んでいます
11/18(土) バイオ&バイオ技術学科 パンフレット撮影第2弾
パンフレット撮影第2弾 part
part

みなさんこんにちは
11/17(金) バイオ&バイオ技術学科 パンフレット撮影
パンフレット撮影 第2弾
第2弾
みなさんこんにちは〜
めっきり寒くなってきましたね
布団から出るのが辛い季節に
なってきました![]()
![]()
![]()
今回のブログは
obm入試広報部
バイオ・バイオ技術学科担当
佐久間がお送りします![]()
![]()
![]()
10月に引き続き11月も来年度の
パンフレット撮影がありました![]()
在校生がとびきりのスマイル
見せてくれているのでまた
その撮影の様子をちょこっと
お伝えします![]()
両手に花ですね![]()
今日の晩御飯何食べる〜
なんて話もしていました 笑
今はモツ鍋食べているのかな![]()

大塚校長も登場!
お忙しい中ありがとうございます![]()
みんな最初は固かった笑顔も徐々にほぐれて
素敵な笑顔を見せてくれていました![]()

バイオ学科の海老澤先生も![]()
いつもありがとうございます![]()

普段はクールな生徒も照れていて
意外な一面![]() 可愛かったです
可愛かったです![]()

カメラマンの方がびっくりするほど
盛り上げ上手!さすがプロだな〜と感動します
皆の自然な笑顔を引き出してくださっていました![]()

3年生にもなるとさすがの貫禄ですね![]()
無添加化粧水を作るための材料を一緒に
買いについて来てくれた優しい先輩です![]()

ポーズも豊富です![]()
![]()
![]()
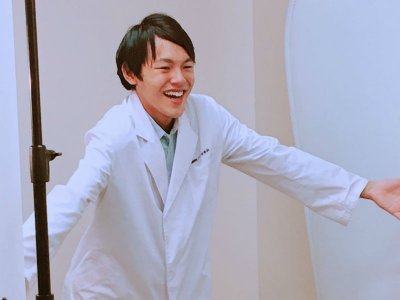
内定もおめでとうございます![]()
全国工業専門学校協会「学生成果報告会」の
ブログでも登場してくれていました![]()
4月からはいよいよ社会人![]()

アミノ酸分析器と3年生![]()

オープンキャンパスをサポートしてくれたり
大舞台でプレゼンをしたり目立つ存在の彼女
いよいよ卒業か〜と寂しくなります![]()
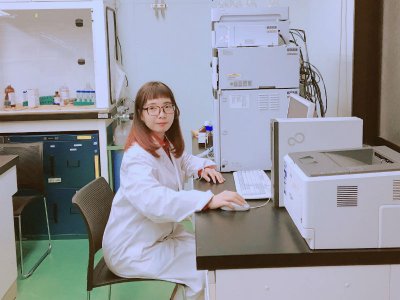
彼女も休日も大塚先生のそばで
細胞培養の勉強をしたり
頑張っていた姿も印象的でした![]()

バイオ技術1年生!
自然な笑顔というフレーズに苦戦していましたが
しっかりと撮影に臨んでくれました![]()


バイオ学科2年生の環境分析
実習班も頑張っていました![]()
さりげなくピースをしている![]()
実習中お邪魔しました![]()
またこの様子は別のブログでお伝えします![]()

色の変化がでるまで記録をとりながら
作業を進めていきます
とても綺麗な色ですね![]()

こんな感じで撮影も順調に進んでいきました![]()
改めてパンフレットの完成楽しみだなと感じました![]()
在校生の皆さんありがとうございました![]()
今日のブログはobmの先生方や
先輩達がたくさん登場しましたね![]()
雰囲気が伝わっていれば嬉しいです![]()
先輩達も今進路選びをしている皆さんと
同じように色々なオープンキャンパスに
参加して大阪バイオメディカル専門学校に
進学を決めてくれました![]()
白衣を着て実験・研究をお仕事にする
バイオ技術者を目指そうかなと
思っている皆さんとっては比較するべき
ポイントがたくさんあります![]()
就職率、離職率、学費、雰囲気・・・
オープンキャンパスに参加して
学校を知るということが将来を
決める大事な決断の材料になりますね![]()
是非脚を運んでみてください![]()
白衣を着て体験する体験授業や
設備のラボツアーなどご用意して
お待ちしています![]()


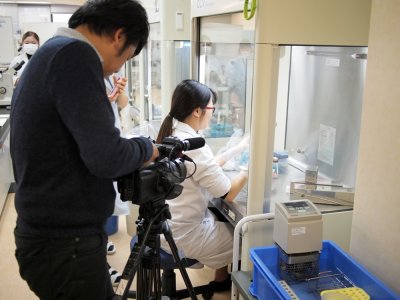

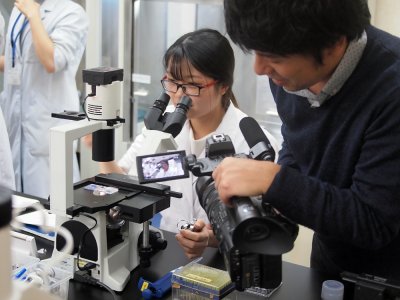


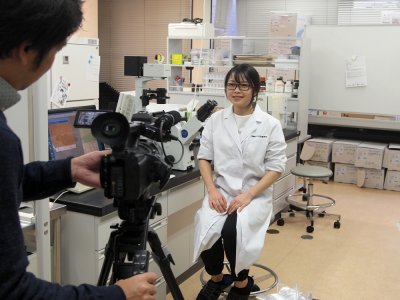
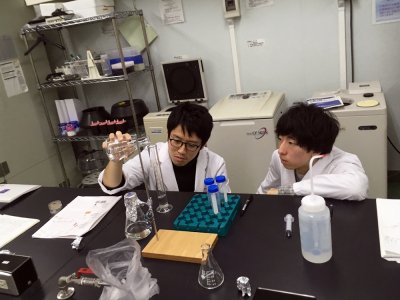
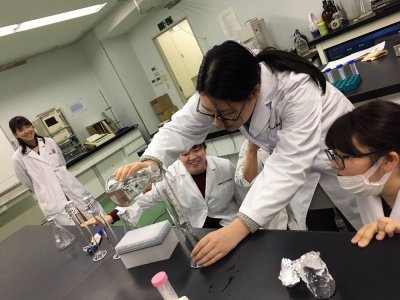

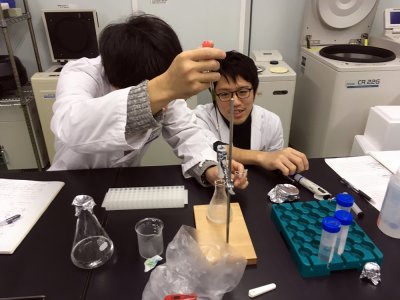









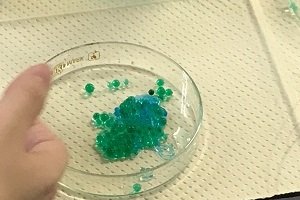

















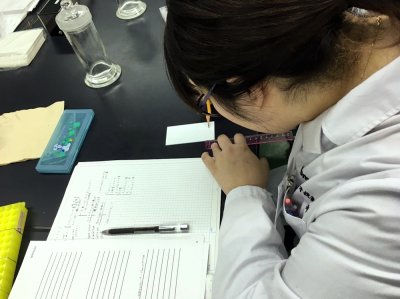

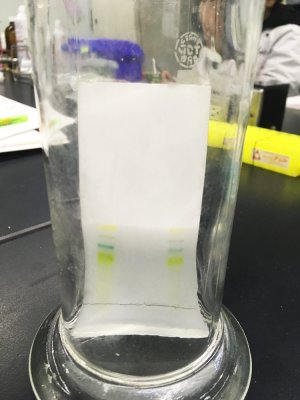









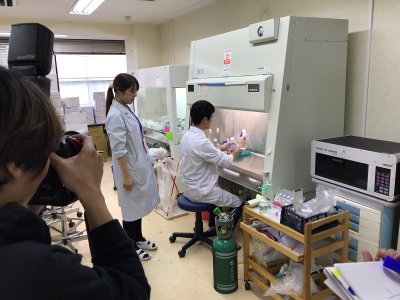




LINEでのお問い合わせも大歓迎